インターホン交換 完全ガイド
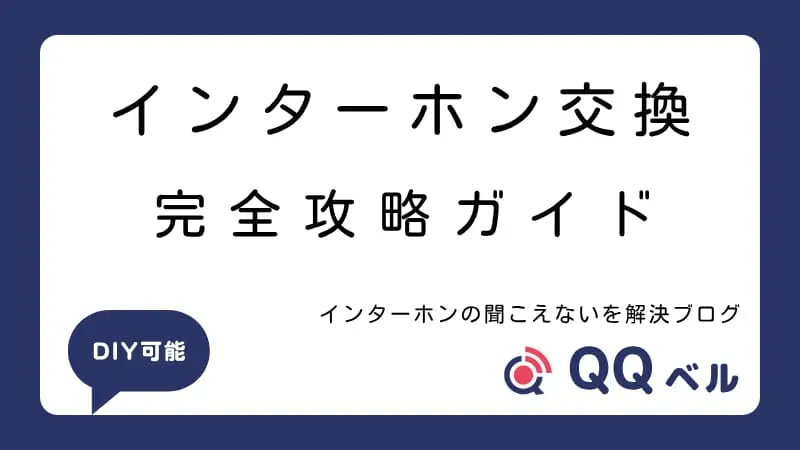
この記事では、インターホンを新しいものに交換したいとお考えの方に向けて、知っておきたい情報をすべてまとめて紹介します。
「自分で交換できるのかな?」「業者さんに頼んだ方がいいのかな?」「費用はどのくらいかかるの?」「どんなインターホンを選べばいいの?」といった疑問にお答えします。

マンションにお住まいの方と戸建てにお住まいの方では注意すべき点が違うため、それぞれのポイントも詳しくご説明します。さらに、新しいインターホンに交換した後、古いインターホンをどうやって処分すればよいかについてもご案内します。
インターホン交換が初めての方でも安心して進められるよう、わかりやすく丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
インターホン交換の理由
お家のインターホンの調子がおかしい、もっと安全にしたい、と思ったことはありませんか?インターホンを新しいものに交換することで、毎日の生活がもっと安心で便利になります。ここでは、どんな時にインターホンを交換したほうがよいのか、わかりやすくご説明します。
古くなったり壊れたりした時
インターホンは家電製品の一つです。テレビや冷蔵庫と同じように、使い続けているうちに古くなって調子が悪くなります。
インターホンの寿命は約10年から15年です。10年以上使っていると、こんな症状が出てきます:
- 声が聞こえにくくなる
- 画面がぼやけて見えにくくなる
- ボタンを押しても反応しない
- 雑音が入る
特に15年以上経った古いインターホンは、メーカーでも修理用の部品がなくなってしまうことがほとんどです。完全に壊れてから慌てるよりも、10年から12年くらいを目安に新しいものに交換するのがおすすめです。
インターホンの調子が悪い時の詳しい症状や対処法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
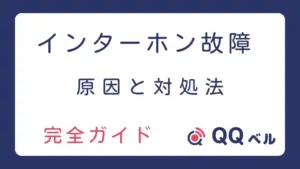
もしインターホンが止まらずに鳴り続けて困っている場合は、こちらの緊急時の対処方法をすぐにご確認ください。
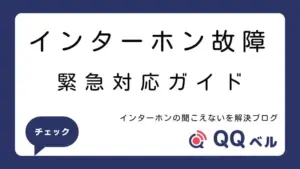
防犯を強化したい時
最近は物騒な事件も多く、お家の安全をもっと守りたいと考える方が増えています。
古いインターホンには画面がついていないものもあり、「誰が来たのかわからなくて怖い」という声をよく聞きます。新しいインターホンに交換すると、こんな安心機能が使えます:
- カメラで訪問者の顔をしっかり確認できる
- 留守の時に来た人を録画で記録できる
- 怪しい人が来ても、姿を見てから対応を決められる
インターホンは家の安全を守る最初の砦です。防犯のためにも、カメラ付きの新しいインターホンへの交換を検討してみてください。
この商品は、面倒な工事をしなくても、ご自分で簡単に取り付けられる、コードレスタイプのテレビ付きインターホンです。

もっと便利に使いたい時
現代のインターホンは、昔とは比べものにならないほど便利になっています。
共働きのご家庭や、日中お家にいないことが多い方には、こんな便利な機能があります:
- スマートフォンにつないで、外出先からでも来訪者と話せる
- 持ち運びできる子機で、お庭や2階にいても応対できる
- 宅配便の再配達を減らせる
インターホンは単に「はい、どちら様ですか?」と話すだけの道具ではなく、毎日の生活をもっとスムーズにしてくれる便利な道具に進化しています。
家族の状況が変わった時
ご家族の構成やライフスタイルが変わると、インターホンに求める機能も変わってきます。
例えば、こんな場合には新しい機能が役立ちます:
- 小さなお子さんがいる:子どもの帰宅をスマートフォンに知らせてくれる
- ペットを飼っている:外出先から室内の様子を見たり、ペットに声をかけたりできる
- 一人暮らしを始めた:防犯機能で安心して生活できる
インターホンは家族みんなの安心と安全を支える、大切な見守り道具にもなっています。
高齢者に対応したい
ご高齢のご家族がいらっしゃる場合、インターホンは特に重要な役割を果たします。
年を重ねると、こんなことが気になってきます:
- 小さな音が聞こえにくくなる
- 細かい文字や画面が見えにくくなる
- ボタン操作が難しくなる
- もしの時の連絡手段が心配
高齢者の方が安心して暮らせるよう、使いやすいインターホンを選ぶことが大切です。
耳が聞こえにくい方やご高齢の方には、こちらの記事がお役に立ちます。
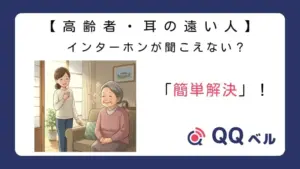
聴覚障害者に対応
耳の聞こえにくい方や、聴覚に障害のある方にとって、従来のインターホンは使いにくいものでした。
新しいインターホンには、こんな配慮された機能があります:
- 来訪者があると、音だけでなく光でも知らせてくれる
- 振動で来客を教えてくれる機能
- 大きくて見やすい画面で、相手の口の動きや表情がよく見える
- 筆談ができるように、画面にメッセージを表示できる機能
聴覚に不安のある方でも、安心して来客対応ができるインターホンが増えています。ご家族みんなが使いやすいものを選ぶことが重要です。
聴覚に障がいのある人方には、こちらの記事がお役に立ちます。
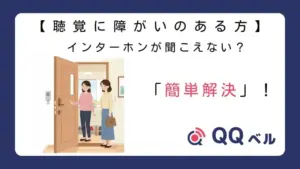
インターホンが聞こえない場所をなくしたい
「インターホンが鳴っているのに気づかなかった」という経験はありませんか?お家が広かったり、2階で過ごすことが多かったりすると、インターホンの音が聞こえないことがあります。
新しいインターホンシステムなら、こんな解決方法があります:
- 家じゅうどこにいても聞こえるよう、複数の場所にスピーカーを設置
- 持ち運びできるワイヤレス子機で、庭仕事中でも応対可能
- スマートフォンアプリで、外出先でも来客がわかる
- お風呂場や寝室など、音が届きにくい場所にも専用の受信機を設置
大切な来客や配達を逃さないよう、お家全体をカバーできるインターホンシステムを検討してみてください。
お家の別の部屋や2階にいる時でも、インターホンの音をしっかり聞く方法については、こちらで紹介しています。
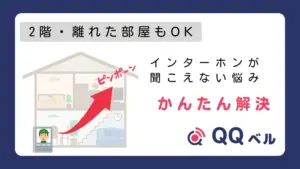
インターホン交換の効果
「インターホンを新しくしたら、本当に今より良くなるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。実は、インターホンを交換すると、毎日の暮らしが驚くほど快適で安全になります。ここでは、新しいインターホンに変えることで、どんな良い変化があるのかを、わかりやすく紹介します。
お家の安全がグッと高まります
新しいインターホンの一番大きな効果は、お家の安全性が大幅にアップすることです。
訪問者の顔がしっかり見える
カメラ付きのインターホンなら、ドアを開ける前に「誰が来たのか」がはっきりわかります。知らない人やセールスの人でも、玄関のドアを開けずに安全にお断りできます。
留守の時も安心
録画機能があるインターホンなら、お出かけ中に誰が来たのかを後から確認できます。大切な荷物の配達や、家族や友人の訪問を見逃すことがありません。もし、不審な人が来た場合の証拠にもなります。
泥棒を寄せ付けない効果
カメラ付きインターホンが付いているお家は、「防犯意識の高い家」という印象を与えます。泥棒や不審者にとって「この家は狙いにくい」と思わせる効果があり、犯罪を未然に防げます。
毎日の生活がとても便利になります
新しいインターホンは、日常生活をもっとスムーズで快適にしてくれます。
外出先からでも来客対応
スマートフォンと連携できるインターホンなら、お買い物中やお仕事中でも、自宅に来た人と話せます。宅配便の時間指定も気にしなくなり、再配達の手間が大幅に減ります。
家じゅうどこにいても対応可能
ワイヤレスの子機があれば、2階にいても、お庭で作業していても、すぐに来客に対応できます。料理の途中で手が離せない時でも、慌てて玄関まで走る必要がありません。
家事がもっと楽になる
洗濯物を干している時や掃除中でも、手を止めずに来客対応ができます。忙しい主婦の方や共働きのご家庭には、特に大きなメリットです。
家族みんなが安心して暮らせます
新しいインターホンは、ご家族全員の安心と安全をサポートします。
お子さんの安全を守る
お子さんの帰宅をスマートフォンに知らせてくれる機能や、留守番中のお子さんが安全に来客対応できる機能があります。「知らない人が来ても、きちんと対応できているかな?」という心配が減ります。
高齢者の方にも優しい
音量を大きくしたり、画面を見やすくしたりできるので、耳や目が不自由になってきたご高齢の方でも安心です。緊急時には自動で家族に連絡してくれる「みまもり機能」もあります。
ペットの様子も確認
外出先から室内カメラでペットの様子を見たり、話しかけたりできる機能もあります。ペットを飼っている方には嬉しい機能です。
火災や災害の時も安心
新しいインターホンには、緊急時の安全機能も充実しています。
火災警報器と連携
火災警報器と連動して、火事の際に自動で家族や近所に知らせてくれる機能があります。一人暮らしの方や高齢者の方には特に重要な機能です。
停電時でも動作
バッテリー機能付きのインターホンなら、停電時でも一定時間は動作します。災害時の安全確保にも役立ちます。
緊急通報機能
体調が悪くなった時や事故の際に、ボタン一つで家族や緊急連絡先に自動で連絡してくれる機能もあります。
お家の価値も上がります
新しいインターホンの設置は、お家そのものの価値向上にもつながります。
住宅の印象アップ
最新の設備が整っているお家は、見た目の印象も良くなります。もし将来お家を売ることになった時にも、良い印象を与えます。
長期的な節約効果
新しいインターホンは省エネ性能も高く、電気代の節約にもなります。また、故障しにくいので、修理費用もかからず、長期的には経済的です。
近所づきあいも良くなります
意外かもしれませんが、インターホンの交換は近所づきあいにも良い影響があります。
来客対応がスムーズ
訪問者をお待たせすることなく、スムーズに対応できるようになります。宅配業者さんや近所の方にも好印象を与えます。
コミュニケーションが取りやすい
画面で相手の顔を見ながら話せるので、より親しみやすい対応ができます。ご近所の方との関係も良好に保てます。
まとめ:生活の質が大きく向上します
インターホンの交換は、単に古い機械を新しくするだけではありません。毎日の暮らしをもっと安全で、便利で、快適にするための大切な投資です。
一度交換すれば長期間使える
インターホンは一度交換すれば10年以上使えるので、長期間にわたって快適な生活を楽しめます。毎日使うものだからこそ、良いものを選ぶ価値があります。
家族全員が恩恵を受ける
お子さんからご高齢の方まで、家族全員が新しいインターホンの便利さを実感できます。みんなが安心して暮らせる環境づくりにつながります。
新しいインターホンで、あなたの暮らしも大きく変わることでしょう。
交換は自分でやる?業者に頼む?
インターホンを新しくしたいけれど、「自分で取り付けできるのかな?」「業者さんに頼んだ方がいいのかな?」と迷っていませんか?実は、お家のインターホンの種類によって、自分でできるものとできないものがあります。ここでは、どちらが良いのかを分かりやすくご説明します。
自分で交換できるかどうかの見分け方
インターホンを自分で交換できるかどうかは、電気がどうやって送られているかで決まります。難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に確認できる方法があります。
コンセントに差し込むタイプ(自分でできる)
室内の親機(話をする機械)にコンセントのプラグが付いていて、壁のコンセントに差し込んであるタイプです。このタイプなら、自分で新しいものに交換できます。家電製品を交換するのと同じ感覚で作業できるので、特別な資格は必要ありません。
乾電池で動くタイプ(自分でできる)
親機の中に乾電池が入っているタイプも、自分で交換可能です。今まで電池交換をしたことがある方なら、このタイプです。
ワイヤレスタイプなら特に簡単(自分でできる)
最近人気なのが、配線工事が全く不要のワイヤレスタイプのインターホンです。このタイプは室内機(親機)と屋外機(子機)が無線でつながっているため、既存の配線を気にする必要がありません。
ワイヤレスインターホンの特徴:
- 配線工事が一切不要
- 電源はコンセント式や充電式で安全
- 取り付けは両面テープやネジ止めだけ
- 賃貸住宅でも設置可能
- 設置場所を自由に選べる
特に、賃貸住宅にお住まいの方や、工事をしたくない方には最適な選択肢です。QQベルでは、設置が簡単で高品質なワイヤレスインターホンを豊富に取り揃えています。
ワイヤレスタイプ おすすめ商品






壁の中の配線につながっているタイプ(業者さんに依頼)
親機がコンセントにもつながっておらず、電池交換をした記憶もない場合は、壁の中の電気配線に直接つながっている可能性があります。この場合は、必ず電気工事士の資格を持った業者さんに依頼してください。
無理に自分でやろうとすると、感電したり火事になったりする危険があります。また、法律でも「資格のない人がやってはいけない」と決められています。
古い呼び鈴からの交換(業者さんに依頼)
今まで「ピンポーン」と音だけが鳴る古い呼び鈴を使っていて、画面付きのインターホンや通話インターホンに変えたい場合は、新しく配線工事が必要になることがほとんどです。この場合も、電気工事士の資格が必要なので、業者さんにお任せしましょう。
ご自分で取り付けを考えている方には、配線工事が全く不要の無線タイプが一番簡単でおすすめです。
このタイプなら、電気工事の知識がなくても安心して設置できます。


マンションの場合(業者さんに依頼)
マンションにお住まいの場合、エントランスのオートロックシステムや、火災報知器などと連動していることがあります。この場合は、建物全体のシステムに影響が出る可能性があるため、必ず専門の業者さんに相談してください。
自分で交換する場合のメリット・デメリット
良い点
費用が安く済む 業者さんに支払う工事費がかからないので、インターホン本体の値段だけで済みます。数千円から数万円程度の節約になります。
自分のペースで作業できる 業者さんの都合を気にせず、自分の好きな時間に作業できます。休日にゆっくり取り組むこともできます。
大変な点
時間と手間がかかる 取り付け方法を調べたり、実際の作業をしたりするのに、思った以上に時間がかかることがあります。
失敗する可能性がある 配線を間違えたり、うまく取り付けられなかったりすると、インターホンが壊れてしまうことがあります。結果的に、修理代で余計にお金がかかってしまう場合もあります。
工具を揃える必要がある ドライバーなどの基本的な工具以外にも、専用の工具が必要になることがあります。
何かあっても自分の責任 作業中にケガをしたり、取り付け後に不具合が起きたりしても、すべて自分で対処しなければなりません。
業者さんに依頼する場合のメリット・デメリット
良い点
安全で確実 電気工事士などの専門家が、豊富な知識と経験で安全に取り付けしてくれます。失敗の心配がほとんどありません。
作業が早い 慣れた業者さんなら、30分から1時間程度で作業が完了します。
専門的な状況にも対応 複雑な配線や特殊な取り付け方法が必要な場合でも、適切に対応してもらえます。
アフターサービスがある 取り付け後に何か問題があっても、業者さんが責任を持って対応してくれることが多いです。
専用の工具を持っている 作業に必要な専門工具をすべて持っているので、追加で購入する必要がありません。
大変な点
費用がかかる インターホン本体の値段に加えて、工事費がかかります。簡単な交換でも1万円前後、配線工事が必要だと3万円以上かかることもあります。
日程調整が必要 業者さんの都合に合わせて、作業日を決める必要があります。
費用の比較
自分で交換する場合
インターホン本体の購入費用だけです。
- 基本的なもの:5,000円~15,000円
- 高機能なもの:10,000円~50,000円
業者さんに依頼する場合
本体費用+工事費がかかります。
- 簡単な交換:本体費用+10,000円~15,000円
- 配線工事が必要:本体費用+30,000円~50,000円
どちらを選べばいい?
自分で交換がおすすめの方
- コンセント式や電池式のインターホンをお使いの方
- DIYが得意で、時間に余裕がある方
- 費用を抑えたい方
- 失敗しても自分で責任を取れる方
業者さんに依頼がおすすめの方
- 壁の配線に直接つながっているタイプをお使いの方
- 安全性を最優先に考える方
- 確実に成功させたい方
- 時間がない方
- アフターサービスを重視する方
- 少しでも不安がある方
費用概算比較(DIY vs 業者)
- DIYの場合: インターホン本体の購入費用のみ。機種によりますが、数千円から数万円程度です。
- 業者依頼の場合: インターホン本体費用に加えて、工事費がかかります。工事費の相場は、簡単な交換であれば1万円前後から、配線工事が必要な場合は3万円以上になることもあります 18。
どちらの方法を選ぶかは、ご自身の技術力、時間、予算、そして何よりも安全性を考慮して慎重に判断してください。少しでも不安がある場合は、無理せず専門業者に依頼することをおすすめします。
DIY vs. 業者依頼 徹底比較
| 比較項目 | DIY | 業者依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | インターホン本体代のみ(比較的安い) | 本体代+工事費+出張費など(比較的高い) |
| 作業時間 | 個人差あり、慣れていないと時間がかかる | 比較的短時間(例:30分~2時間程度) |
| 必要なスキル・知識 | ある程度の電気知識、工具の扱い、説明書読解力 | 不要(業者が全て対応) |
| 安全性 | 自己責任(特に電源直結式は危険) | 高い(有資格者が安全に作業) |
| 法的要件(電源直結式の場合) | 電気工事士資格が必須(無資格作業は違法) | 業者が有資格者を手配 |
| 仕上がりの確実性・見栄え | 個人差あり、失敗のリスクも | プロによる確実な仕上がり、配線処理も綺麗 |
| 保証 | 基本的になし(製品自体の初期不良はメーカー保証) | 工事保証が付く場合あり、製品保証も有効 |
| メリット | 費用を抑えられる、自分のペースでできる | 安全・確実・スピーディー、専門知識不要、保証が付く場合がある |
| デメリット | 時間と手間、失敗リスク、安全性自己責任、保証なし | 費用が高い |
| おすすめな人 | 電気知識がありDIYに慣れている人、費用を最優先したい人(電源プラグ式・乾電池式に限る) | 安全・確実性を重視する人、DIYに自信がない人、時間がない人、電源直結式の交換が必要な人 |
まとめ
インターホンの交換は、タイプによって自分でできるものとできないものがあります。最も大切なのは安全性です。少しでも「難しそうだな」「危険かもしれない」と感じたら、無理をせず専門の業者さんに相談することをおすすめします。
長期的に考えると、多少費用がかかっても、安全で確実な業者さんによる工事の方が、結果的に安心できる場合も多いです。まずは、現在のインターホンがどのタイプなのかを確認することから始めてみてください。
DIYでのインターホン交換:完全ガイド
ご自分でインターホン交換をお考えの方へ、安全で正しい手順を紹介します。工具の準備から実際の取り付け、よくある失敗の回避方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説いたします。
自分で交換できるインターホンの見分け方
まず、お使いのインターホンが自分で交換できるタイプかどうかを確認しましょう。
コンセントから電気を取るタイプ
室内機(お家の中の機械)にコンセントのプラグが付いていて、壁のコンセントに差し込んであるタイプです。このタイプなら自分で交換できます。家電を交換するのと同じ感覚で作業できるので、特別な知識や資格は不要です。
電池で動くタイプ
室内機の中に乾電池が入っているタイプも自分で交換可能です。今まで電池交換をしたことがある方なら、このタイプです。
無線で通信するタイプ
最近人気の無線タイプは、配線工事が全く不要で、最も簡単に交換できるタイプです。室内機と玄関機が電波で通信するため、既存の配線を気にする必要がありません。賃貸住宅の方や、工事をしたくない方に最適です。
電話と一体型のインターホン
固定電話とインターホンが一体となったタイプの機器も存在します。多くはコンセント式で、親機(電話機)とインターホン子機がセットになっていますが、配線方法や設置状況によっては自分で交換できる場合と、専門業者による工事が必要な場合があります。
交換の際は、電話線とインターホン配線の両方を確認し、必要に応じてメーカーの説明書や専門家に相談しましょう。
壁の配線に直接つながっているタイプ(業者に依頼)
室内機がコンセントにもつながっておらず、電池交換をした記憶もない場合は、壁の中の電気配線に直接つながっている可能性があります。このタイプは危険なので、必ず電気工事士の資格を持った業者に依頼してください。
現在のインターホンの確認方法
室内機の確認手順
室内機を壁から取り外してみましょう。多くの場合、本体を下から上にスライドさせると壁の取り付け金具から外れます。
- 電源プラグが見えれば「コンセント式」
- 電池ボックスがあれば「電池式」
- 太い電線と細い線が壁から直接出ていれば「配線直結式」(業者依頼必須)
配線の状態をチェック
玄関機との通信には、通常2本の細い線(チャイムコード)が使われています。この配線が使えるかどうか、線の本数や状態を確認します。
古い呼び鈴からカメラ付きインターホンに交換する場合、映像を送るための配線が別途必要になることが多く、業者への依頼をおすすめします。
必要な道具と材料
基本的な道具
プラスドライバー ネジの取り外し・取り付けに必須です。サイズ違いで数種類あると便利です。
マイナスドライバー
古い機種のカバー取り外しや端子接続で使用することがあります。
あると便利な道具
ゴム手袋 感電防止のために着用をおすすめします。
絶縁テープ 配線の接続部を保護するために使用します。
懐中電灯 壁の内部や暗い場所での作業時に役立ちます。
脚立 室内機や玄関機が高い位置にある場合に必要です。
水平器 取り付け金具をまっすぐ設置するためにあると便利です。
材料
新しいインターホン本体 選定した機種(室内機・玄関機セット)
取り付け金具 通常、新しいインターホンに付属しています。
ネジ類 通常付属していますが、壁の材質によっては別途用意が必要な場合もあります。
防水材料 玄関機を雨風から保護するために、防水カバーやコーキング材があると安心です。
交換作業の手順
作業前の準備
安全の確保
- コンセント式:必ず電源プラグをコンセントから抜く
- 電池式:室内機・玄関機の電池を抜く
作業中の表示 玄関ドアに「インターホン交換作業中。ご用件はノックでお願いします」などの張り紙をしておくと親切です。
写真撮影 取り外す前に、既存のインターホンの配線状況を写真に撮っておくと、後で分からなくなった場合の参考になります。
玄関機の交換手順
古い玄関機の取り外し
- 本体下部や側面のネジを緩めてカバーを外します
- 裏側の配線(2本の細い線)を固定しているネジを緩めて外します
- 壁の取り付け枠のネジを外して取り外します
新しい玄関機の取り付け
- 新しい取り付け枠を壁の適切な位置にネジで固定します
- 壁から出ている2本の線を新しい玄関機の端子に接続します
- 配線した玄関機本体を取り付け枠にはめ込み、ネジで固定します
- 雨水の侵入を防ぐため、壁との隙間をコーキング材で埋めます
室内機の交換手順
古い室内機の取り外し
- 本体を上にスライドさせて壁の取り付け金具から外します
- 裏側の配線(玄関機からの線とコンセント線)を外します
- 壁の固定金具のネジを緩めて取り外します
新しい室内機の取り付け
- 新しい固定金具を壁の適切な位置にネジで固定します
- 壁から出ている線を新しい室内機の端子に接続します
- 配線した室内機本体を取り付け金具にスライドして設置します
- コンセット式の場合は、電源プラグをコンセントに差し込みます
無線タイプの設置手順
室内機の設置 コンセントの近くに設置します。壁掛けも可能ですが、卓上スタンドが付属している機種もあります。
玄関機の設置 多くは電池式で、配線工事は不要です。付属のネジや両面テープで玄関ドア横の適切な場所に取り付けます。
通信設定 室内機と玄関機を無線で通信させるための設定を行います。取扱説明書に従って設定してください。
動作確認
すべての取り付けが終わったら、以下の確認を行います。
基本動作の確認
電源の確認 室内機の電源を入れます(コンセントを差す、電池を入れるなど)。
呼び出しテスト 玄関機の呼び出しボタンを押し、室内機で音が正常に鳴るか確認します。
通話テスト 室内機と玄関機の間で実際に通話し、音声が途切れたりしないか確認します。
画面の確認 カメラ付きの場合、室内機の画面で玄関先の映像を確認し、カメラの向きや角度が適切かチェックします。
安全対策と注意点
感電防止の徹底
必ず電源を切る 作業前には必ず電源プラグを抜くか、電池を外してください。
ゴム手袋の着用 電源を切った後でも、念のためゴム手袋を着用して作業することをおすすめします。
配線直結式は触らない 壁の配線に直接つながっているタイプは、絶対に自分で作業しないでください。
配線ミスの防止
写真で記録 古いインターホンを取り外す前に、配線の接続状況をスマートフォンで撮影しておきましょう。
正しい接続 配線は奥までしっかり差し込み、ネジで固定してください。接触不良の原因になります。
絶縁処理 配線を接続した後は、むき出しになった部分がないか確認し、必要であれば絶縁テープで保護してください。
確実な取り付け
しっかり固定 室内機や玄関機は、ぐらつかないようにしっかりとネジで固定してください。
防水処理 玄関機は屋外に設置されるため、壁との隙間を防水カバーやコーキング材で埋めることをおすすめします。
よくある失敗と対策
音が鳴らない
原因と対策
- 電源プラグや電池が正しく接続されているか確認
- 配線が奥までしっかり差し込まれているか確認
- 作業前の写真と照らし合わせて接続に間違いがないか確認
画面に映像が映らない
原因と対策
- カメラの向きや角度を調整
- 配線の接続を再確認
- レンズに汚れが付いていないかチェック
取り付けがぐらつく
原因と対策
- 取り付け金具が壁にしっかり固定されているか確認
- ネジの締め直し
- 壁の材質に適したネジやアンカーを使用
部品を紛失・破損
対策
- 作業前に小さなトレイを用意して部品を管理
- 破損した部品はメーカーから取り寄せるか、同等品を探す
- 予備のネジがあればそれを使用
作業が困難な場合の対処法
中断時の安全確保
作業中に困難を感じたら、まずは安全を確保してください。電源を切った状態にして、現状を写真に撮るなどして記録します。
専門家への相談
取扱説明書を再確認しても解決しない場合は、購入した販売店やメーカーのサポートセンターに問い合わせてみましょう。
業者への引き継ぎ
自力での解決が困難だと判断した場合は、無理をせず専門業者に作業の引き継ぎを依頼するのが賢明です。これまでの作業内容や問題点を正確に伝えることが重要です。
まとめ
DIYでのインターホン交換は、正しい手順と安全対策を守れば、十分に可能な作業です。しかし、最も重要なのは安全性です。少しでも不安や疑問があれば、無理をせず専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
特に、配線直結式のインターホンや、マンションのオートロックシステムと連動している場合は、必ず専門業者に依頼してください。安全で快適なインターホンライフを楽しむために、適切な判断を心がけましょう。
プロに頼むインターホン交換
インターホン交換で「自分でやるのは不安」「失敗したくない」とお考えの方には、専門業者への依頼がおすすめです。ここでは、良い業者の見分け方から費用の目安、注意すべき業者の特徴まで、分かりやすく紹介します。
信頼できる業者の見つけ方
良い業者を選ぶためには、いくつかのチェックポイントがあります。
必要な資格を持っているか確認
インターホンの交換、特に壁の配線に直接つながっているタイプの場合は、「第二種電気工事士」という国家資格が必要です。業者のホームページに資格情報が載っているか、見積もりの時に直接確認しましょう。
資格のない業者に頼むと、火事や感電の危険があるだけでなく、もし事故が起きた時に保険がきかない場合もあります。
過去の実績と評判をチェック
口コミサイトを活用 ミツモア、くらしのマーケット、ゼヒトモなどの比較サイトで、実際に利用した人の感想を読んでみましょう。良い評価だけでなく、悪い評価とそれに対する業者の対応も確認すると、より正確な判断ができます。
施工事例を確認 業者のホームページで、インターホン交換の作業写真が載っていれば、技術力や仕上がりの質を確認できます。
複数の業者から見積もりを取る
最低でも2〜3社、できればそれ以上の業者から見積もりをもらって比較しましょう。これにより、だいたいの相場が分かります。
見積書の中身をチェック 「工事一式」といった曖昧な書き方ではなく、インターホン本体の値段、基本工事費、出張費、配線工事費などが項目ごとに明記されているかを確認してください。分からない部分は遠慮なく質問しましょう。
追加料金の有無を確認 見積もり以外に追加でお金がかかる可能性があるか、あるとすればどんな時かを事前に聞いておくことが大切です。
対応の良さを見る
電話やメールの対応 問い合わせ時の電話応対やメールの返信の早さ、説明の分かりやすさも重要な判断材料です。専門用語ばかり使わず、分かりやすく説明してくれる業者を選びましょう。
親身になってくれるか お客さんの立場になって相談に乗ってくれるか、コミュニケーションが取りやすいかも確認ポイントです。
保証内容を確認
工事後の保証内容やアフターサービスについても、契約前に必ず確認しておきましょう。工事保証の期間や範囲、もし不具合が起きた場合の対応を明確にしておくことで、後のトラブルを防げます。
地元業者か大手業者か
地元の電気店や工務店 フットワークが軽く、親身な対応が期待できる場合があります。
大手家電量販店やリフォーム会社 広いネットワークや充実した保証制度が魅力ですが、実際の作業は下請け業者が行うこともあり、担当者によって対応に差が出ることがあります。
それぞれの良い点・悪い点を考えて選びましょう。
工事費用の目安
インターホン交換にかかる費用は、新しいインターホンの機種代金と工事費の合計です。
インターホン本体の値段
音声のみの基本タイプ 数千円から購入できます。
画面付きのテレビドアホン 1万円〜6万円程度が一般的です。
録画機能付きの高機能タイプ 10万円を超えることもあります。
基本工事費
既存のインターホンを取り外して新しいものを取り付ける基本的な作業で、7,000円〜15,000円程度が目安です。
出張費
業者が家まで来るのにかかる費用で、3,000円〜5,000円程度が一般的です。業者によっては基本工事費に含まれている場合もあります。
追加工事が必要な場合
配線工事 古い呼び鈴からインターホンに変更する場合や、設置場所を変える場合に必要です。5,000円〜20,000円程度が目安です。
壁の穴あけ作業 新しいインターホンのサイズが違う場合や、新しく設置する場合に必要です。5,000円〜が目安です。
防水処理 玄関機の周りを防水材で埋める作業で、3,000円〜が目安です。
コンセント増設 近くにコンセントがない場合のコンセント工事で、10,000円〜20,000円程度が目安です。
これらの費用はあくまで目安で、実際の金額は業者や工事内容によって大きく変わります。必ず複数の業者から詳しい見積もりを取って比較することが重要です。
悪質な業者にご注意
残念ながら、インターホン交換を含むリフォーム業界には、不当に高い料金を請求したり、手抜き工事をしたりする悪質な業者が存在します。
よくある悪質な手口
無料点検と不安を煽る手口 「近所で工事していたら、お宅のインターホンが危険な状態なのが見えました」「無料で点検しますよ」などと言って訪問し、実際には問題ない部分を「このままでは火事になる」と大げさに言って、不安を煽って高額な契約を迫ります。
大幅割引で即決を迫る手口 「今日契約すれば半額にします!」「特別価格で安くします」などと魅力的な条件を出して、冷静に考える時間を与えずに契約させようとします。実際には元の価格設定が高く、割引後も相場より高額なケースがほとんどです。
契約内容が曖昧な手口 口頭での説明だけで契約書をきちんと作らなかったり、「工事一式○○円」といった曖昧な見積もりで詳細を示さず、工事が始まってから「これも別料金」「あれも追加費用」と次々に請求してくるケースです。
有名な会社を装う手口 電力会社やガス会社、有名なメーカーの関連会社などを名乗って信用させ、家に入り込もうとします。
悪質業者を避ける方法
その場で契約しない どんなに魅力的な条件を出されても、その場で契約したり、書類にサインしたりするのは絶対に避けましょう。「家族と相談してから決めます」「他の業者からも話を聞いてみます」とはっきり伝えることが大切です。
身元をしっかり確認 業者の会社名、担当者名、住所、連絡先などを明確に確認し、名刺をもらいましょう。インターネットで会社の評判を調べることも重要です。
複数の業者から見積もり 相見積もりは、適正価格を知る最も良い方法です。
契約書の内容を詳しく確認 工事内容、使う材料、金額、保証内容などを隅々まで確認し、少しでも分からない点があれば納得いくまで説明を求めましょう。
きっぱりと断る 不要だと感じたり、少しでも怪しいと感じたりした場合は、はっきりとした態度で断ることが大切です。
ドアを安易に開けない 知らない訪問者には、まずインターホン越しに用件や身元を確認しましょう。録画機能付きのインターホンなら、やり取りを記録しておくことも有効です。
トラブル時の相談先
もし、悪質な業者と契約してしまったり、トラブルに巻き込まれたりした場合は、一人で悩まずに専門機関に相談しましょう。
消費者ホットライン「188」188(いやや!) ※最寄りの消費生活センターに自動で接続され、専門の相談員がアドバイスしてくれます。
土日・祝日も相談可能な窓口(一部抜粋)
- 東京(土日):03-5614-0189(10:00~12:00、13:00~16:00)
- 大阪(日曜):06-6203-7650(10:00~12:00、13:00~16:00)
- 北海道(土曜):011-612-7518(13:00~16:00)
住宅リフォーム紛争処理支援センター 住宅リフォームに関する専門的な相談や問題解決の支援をしています。
| 名称 | 電話番号 | 受付時間 | URL |
|---|---|---|---|
| 住まいるダイヤル(全国共通・固定電話) | 03-3556-5147 | 平日10:00~17:00(土日祝・年末年始除く) | https://www.chord.or.jp |
| 住まいるダイヤル(ナビダイヤル) | 0570-016-100 | 平日10:00~17:00(土日祝・年末年始除く) | https://www.chord.or.jp |
| 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(財団概要) | 03-3556-5101 | 平日 | https://www.chord.or.jp/chord_official/index.html |
| 電話相談予約フォーム | – | – | https://www.chord.or.jp/consult_tel/reservation_form/index.ht |
保証内容の確認ポイント
インターホン交換後の安心のために、保証内容をしっかり確認しておくことが重要です。保証には「メーカー保証」と「工事保証」の2種類があります。
メーカー保証(製品保証)
対象 インターホン本体の製造上の欠陥や、普通に使っていて自然に起きた故障が対象です。
保証期間 一般的に購入日から1年間ですが、機種やメーカーによって違う場合があります。
対象外になるもの 取扱説明書に反する使い方、落雷や水害などの天災、年月が経って起きる見た目の変化、電池などの消耗品、お客さんの不注意による破損などは保証の対象外です。
手続き方法 故障した場合は、保証書に書かれたメーカーのサポート窓口に連絡し、指示に従って修理や交換の手続きを行います。購入日を証明する書類(レシートなど)が必要になることが多いです。
工事保証(施工保証)
対象 インターホンの取り付け工事の不備(配線間違い、取り付け不良など)が原因の不具合が対象です。
保証期間 業者によって違い、数ヶ月から数年(1年〜5年など)と幅があります。契約前に必ず確認しましょう。
対象外になるもの 製品自体の故障、お客さんによる改造や間違った使い方、天災などが原因の場合は対象外になることがあります。
手続き方法 不具合が起きた場合は、工事を頼んだ業者に連絡し、状況を説明して対応をお願いします。
保証で特に大切なポイント
2つの保証の違いを理解する トラブルの原因が製品にあるのか?工事にあるのか?で、責任の所在と連絡先が変わるため、この区別はとても重要です。
保証書は必ず紙でもらって保管 口約束ではなく、保証期間、保証範囲、対象外の内容、連絡先などが書かれた保証書を必ず発行してもらい、製品の保証書と一緒に大切に保管しておきましょう。
対象外の内容を事前に確認 どんな場合に保証が使えないのかを事前に把握しておくことで、後のトラブルを避けられます。
手続きの流れを確認 もしの時にスムーズに対応できるよう、誰に連絡して、どんな情報が必要になるのかを事前に確認しておくと安心です。
メーカー保証 vs 工事保証 比較表
| 比較項目 | メーカー保証(製品保証) | 工事保証(施工保証) |
|---|---|---|
| 保証対象 | インターホン機器自体の製造上の欠陥、自然故障 | 取り付け工事の不備(配線ミス、設置不良など)に起因する不具合 |
| 保証主体 | 製品メーカー | 工事を施工した業者 |
| 一般的保証期間 | 通常1年程度(機種・メーカーにより異なる、延長保証ありの場合も) | 業者により異なる(数ヶ月~数年、例:1~5年) |
| 主な免責事項 | 誤使用、天災、経年劣化、消耗品、お客様の過失による破損など | 製品自体の故障、お客様による改造、天災など |
| 申請方法・連絡先 | メーカーのサポート窓口(保証書記載) | 工事を依頼した業者 |
まとめ
インターホン交換をプロに頼む場合、良い業者選びが最も重要です。資格の確認、複数の見積もり比較、保証内容の確認をしっかり行い、悪質な業者の手口を知って身を守ることが大切です。
少し手間はかかりますが、これらのポイントを押さえることで、安心して長期間使えるインターホンの交換が実現できます。分からないことがあれば、遠慮なく業者に質問し、納得してから契約することをおすすめします。
住居タイプ別:インターホン交換の注意点
お住まいのタイプによって、インターホン交換の進め方や気をつけるポイントが大きく変わります。戸建て、マンション、賃貸物件、公団住宅それぞれの特徴を分かりやすくご説明します。
戸建て住宅の場合
戸建て住宅では、比較的自由にインターホン交換ができますが、いくつか注意点があります。
設置場所を選ぶ時のポイント
室内機も玄関機も、基本的には好きな場所に設置できます。ただし、玄関機は屋外に設置するため、雨風や直射日光の影響を考える必要があります。
おすすめの設置場所
- 軒下など雨がかからない場所
- 防水カバーで保護できる場所
- カメラ付きの場合は、訪問者の顔がよく映る位置
- 逆光にならない向きを選ぶ
電気の確保について
コンセント式の場合 室内機の近くにコンセントがない場合は、新しくコンセントを作る工事が必要になることがあります。
配線直結式の場合 新しく電気配線工事が必要になる場合があります。この場合は電気工事士の資格が必要なので、必ず業者に依頼してください。
外壁の工事について
玄関機の設置や配線のために外壁に新しく穴を開ける場合は、建物の構造や防水に影響が出ないよう注意が必要です。不安な場合は専門業者に相談しましょう。
マンション・集合住宅の場合
マンションでのインターホン交換は、戸建てに比べて制約が多く、慎重な対応が必要です。
管理規約の確認が最重要
まず、マンションの管理規約を確認して、インターホンが「専有部分」(個人のもの)か「共用部分」(みんなのもの)かを調べる必要があります。交換に関する決まりごと(許可が必要か、手続き、費用負担など)も確認しましょう。
管理組合への相談と承認
多くの場合、インターホンの交換には管理組合への事前相談と承認が必要です。理事会での話し合いや、場合によっては総会での決議が必要になることもあります。申請から承認までの時間も考えておきましょう。
オートロックとの連携に注意
エントランスのオートロックシステムと各住戸のインターホンがつながっている場合、個人が勝手にインターホンを交換することは原則としてできません。システム全体に影響し、他の住民の方に迷惑をかける可能性があるためです。
この場合は、マンション全体で一斉に交換することが一般的です。
火災報知器との連携
住戸内のインターホンが火災報知器やガス警報器とつながっている場合も、対応する機種を選ぶ必要があり、個人での安易な交換は避けるべきです。
費用負担について
専有部分のインターホンでも、故障の原因や規約によっては、管理組合が費用を負担するケースや、一部補助が出るケースもあります。マンション全体で一斉交換する方が、個別に交換するよりも費用を抑えられることもあります。
マンションでのインターホン交換は、個人の希望だけでなく、マンション全体のシステムや他の住民との調和を考えることが最も重要です。トラブルを避けるためにも、必ず管理組合や管理会社に相談し、指示に従いましょう。
賃貸物件の場合
賃貸アパートや賃貸マンションでは、インターホンの交換に大家さんや管理会社の許可が不可欠です。
事前許可の取得
インターホンは物件の設備の一部と見なされるため、交換前に必ず大家さんまたは管理会社に相談し、書面で承諾をもらう必要があります。無断で交換した場合、契約違反となり、退去時にトラブルになったり、修繕費用を請求されたりする可能性があります。
費用は誰が負担するか
大家さん負担になる場合 年月が経って自然に壊れた場合は、大家さん負担で修理・交換してもらえることがあります。
入居者負担になる場合 入居者の希望でより良い機能のインターホンに変えたい場合は、原則として入居者の自己負担となります。
退去時の原状回復について
賃貸契約には通常「原状回復義務」が定められており、退去時には入居前の状態に戻す必要があります。交換したインターホンも、退去時には元の機種に戻すか、新しいインターホンをそのままにして良いかを事前に大家さんと決めておくことが重要です。
外壁工事は基本的に不可
インターホンの取り付けのために新たに外壁に穴を開けるような工事は、建物の構造や価値に影響するため、基本的に許可されないことが多いです。既存の設備を利用した交換が前提となります。
賃貸物件での設備変更は、常に「退去時に元に戻すこと」を念頭に置き、大家さんや管理会社とのコミュニケーションを密に取ることがトラブル回避の鍵です。
公団住宅(UR都市機構など)の場合
UR都市機構などの公団住宅では、インターホン交換に関して独自のルールが定められています。
模様替え申請と承諾
UR賃貸住宅で既存のインターホンをモニター付きインターホンなどに交換する場合、費用は原則としてお客様負担となり、事前にUR都市機構の管理サービス事務所等へ「模様替え等承諾申請書」と必要書類(交換機種のパンフレットや図面など)を提出し、承諾を得る必要があります。
交換できない場合もある
現在使用しているインターホンに、自動火災警報機能や集合玄関の解錠機能などが内蔵されている場合は、交換できないことがあります。
原状回復義務の免除について
交換後のインターホンがUR都市機構の定める仕様に適合している場合など、一定の条件を満たせば、退去時の原状回復義務が免除されることもあります。これも事前に確認が必要です。
手続きの進め方
公団住宅にお住まいの方は、まずUR都市機構の「住まいのしおり」を確認したり、管轄の管理サービス事務所や住まいセンターに問い合わせたりして、正しい手続き方法や条件を確認してください。
住居タイプ別まとめ
戸建て住宅
- 比較的自由に交換可能
- 設置場所や電源確保に注意
- 外壁工事は慎重に
マンション・集合住宅
- 管理規約の確認が最優先
- 管理組合への相談・承認が必要
- オートロックとの連携に注意
- システム全体への影響を考慮
賃貸物件
- 大家さん・管理会社の許可が必須
- 費用負担を事前に確認
- 原状回復義務を忘れずに
- 外壁工事は基本的に不可
公団住宅(UR等)
- 模様替え申請が必要
- 特殊機能付きは交換不可の場合あり
- 原状回復義務免除の可能性あり
- 管理事務所への相談が重要
どの住居タイプでも、事前の確認と相談が重要です。思わぬトラブルを避けるためにも、必要な手続きを踏んで、安心してインターホン交換を進めましょう。住居タイプ別:インターホン交換の注意点
住居タイプ別 インターホン交換のチェックポイント
| 住居タイプ | 確認事項 | 主な注意点 | 費用負担の傾向 |
|---|---|---|---|
| 戸建て | 設置場所の自由度、電源確保方法、外壁加工の要否 | 防水処理、カメラ画角、配線ルートの美観 | 原則自己負担 |
| マンション(管理組合あり) | 管理規約(専有/共用部分、交換規定)、管理組合への申請・承認プロセス、オートロック・他設備との連携 | 個人での勝手な交換は原則不可、システム全体への影響考慮、一斉交換の検討 | 規約や状況による(自己負担、管理組合負担、一部補助など) |
| 賃貸物件 | 大家・管理会社への事前相談と書面での許可取得、原状回復義務の確認 | 無断交換は契約違反リスク、外壁穴あけ不可、退去時の取り扱いを明確に | 原則自己負担(故障時は大家負担の場合も) |
| 公団住宅(URなど) | URの規定確認(模様替え承諾申請)、交換可能機種の制限、原状回復義務の免除条件 | 自動火災報知・集合玄関解錠機能付きは交換不可の場合あり、必ず事前申請と承諾が必要 | 原則自己負担 |
インターホン設置場所のポイント
インターホンの使いやすさや防犯効果は、どこに設置するかで大きく変わります。室内機と玄関機それぞれの最適な設置場所を選ぶコツと、よくある失敗例を紹介します。
室内機の設置場所
室内機は、家族みんなが使いやすく、生活の邪魔にならない場所を選ぶことが大切です。
応答しやすい場所を選ぶ
リビングやダイニング 家族が最も長く過ごす場所に設置すれば、呼び出しに気づきやすく、すぐに応答できます。ソファの横の壁や、リビングの入り口近くの壁などがおすすめです。
キッチン お料理中でも応対しやすい場所ですが、換気扇や調理器具の音で呼び出し音が聞こえにくくなる場合もあります。
廊下 家の中心に近い廊下なら、各部屋からアクセスしやすく、呼び出し音が家全体に響きやすいメリットがあります。
2階建ての場合 2階への階段の上がり口付近や、2階のホールも選択肢になります。ワイヤレス子機を併用するとより便利です。
画面の見やすさを考える
画面付きインターホンの場合、画面が見やすい高さに設置することが重要です。
適切な高さ 床から120cm〜150cm程度の高さが、立った状態でも座った状態でも確認しやすく、家族みんなにとって使いやすいとされています。
避けるべき高さ 高すぎたり低すぎたりすると、画面が見にくくストレスになります。
生活動線と安全性
邪魔にならない場所 日常的に人が通る場所に設置すると、ぶつかったり邪魔になったりする可能性があります。生活動線を考えて、邪魔にならない壁面を選びましょう。
子どもの安全 小さなお子さんがいるご家庭では、子どもの手が届きにくい高さ(床から約140cm〜150cm程度)に設置することで、誤った操作を防げます。
避けるべき場所(失敗例)
テレビの近く テレビの音で呼び出し音が聞こえにくくなります。
収納扉の前 収納扉の開け閉めの邪魔になってしまいます。
窓の近く 外からの視線が気になったり、日光の反射で画面が見えにくくなったりします。
配線が見える場所 お部屋の見た目が悪くなってしまいます。
玄関機の設置場所
玄関機は、訪問者が最初に触れる部分であり、防犯カメラとしての役割も担うため、設置場所がとても重要です。
訪問者の使いやすさ
見つけやすい位置 訪問者が見つけやすく、ボタンを押しやすい位置に設置するのが基本です。一般的には、玄関ドアのすぐ横や門柱などが選ばれます。
適切な高さ 地面から120cm〜140cm程度が、多くの人にとって無理なくボタンを押せる高さです。
カメラの性能を活かす位置
顔がしっかり映る位置 カメラ付きインターホンの場合、訪問者の顔や姿がはっきりと映るように、カメラの視野が広く取れる位置を選びましょう。
防犯効果を高める位置 不審者の侵入経路となりやすい場所も映るように設置すると、防犯効果が高まります。
環境への配慮
雨風から守る 屋外に設置するため、雨風や直射日光の影響をできるだけ受けにくい場所を選びましょう。
保護対策 軒下や専用の防水カバーを取り付けるなどの対策で、故障のリスクを減らし、長持ちできます。
カメラの逆光対策
カメラ付きインターホンを設置する際、カメラの位置によっては訪問者の顔が暗く映って、誰だか分からないことがあります。これは「逆光」が主な原因です。
逆光になりやすい場所
直射日光が当たる場所 カメラに直射日光や強い照明が直接当たる場所では逆光になりやすくなります。
光を反射する場所 カメラの正面が白い壁など、光を強く反射する場所も逆光の原因になります。
背後が明るすぎる場所 訪問者の背後が非常に明るくなる環境(日中の空が広く映り込む、明るい照明が背景になるなど)も避けましょう。
逆光を防ぐ方法
設置場所を工夫 上記の逆光になりやすい場所への設置は避けるのが基本です。
逆光補正機能付きを選ぶ どうしても避けられない場合は、逆光補正機能が付いているインターホンを選ぶと、ある程度映像の見やすさを改善できます。
角度と日除けの工夫 玄関機の設置角度を調整したり、日除けを設けたりするなどの工夫も有効です。
設置場所を決める前に
事前の確認作業
間取り図でシミュレーション 間取り図を見ながら生活動線をイメージしてみましょう。
実際に立ってみる 設置したい場所に実際に立ってみて、使いやすさを確認することも大切です。
家族みんなの意見 家族全員が使いやすい場所かどうか、みんなで話し合って決めましょう。
位置変更にかかる費用
もしインターホンの位置を変更する場合、一般的に2万円から5万円程度の追加費用がかかることがあります。これは電気工事や配線の移動、壁の穴あけなど専門的な作業が必要になるためです。
そのため、最初に設置場所をしっかり検討しておくことが、後の費用を抑えることにもつながります。
まとめ
インターホンの設置場所は、毎日の使いやすさと安全性に大きく影響します。室内機は家族が応答しやすく生活の邪魔にならない場所、玄関機は訪問者が使いやすく防犯効果の高い場所を選ぶことが重要です。
また、カメラ付きの場合は逆光対策も忘れずに。事前にしっかり検討して、長期間快適に使えるインターホンにしましょう。
古いインターホンの処分とトラブル対処
インターホンの交換が無事に終わっても、まだやるべきことがあります。古いインターホンの適切な処分と、もし新しいインターホンに不具合が起きた場合の対処法について分かりやすくご説明します。
古いインターホンの正しい処分方法
取り外した古いインターホンや部品は、環境への配慮とお住まいの地域のルールに従って正しく処分する必要があります。
お住まいの地域のゴミ分別ルールを確認
基本的な処分方法 最も基本的な処分方法は、お住まいの地域が定めるゴミ分別ルールに従うことです。インターホンはプラスチックや金属部品でできているため、「燃えないゴミ」または「粗大ゴミ」として扱われることが多いです。
分別の仕方 地域によって分別方法が違うため、必ず地域のホームページやゴミ分別ガイドで確認してください。例えば、電源コードは根元から切断し、束ねて「燃えないゴミ」として出すよう指示されることがあります。
粗大ゴミの基準 一辺の長さが30cmや50cmを超えるものは粗大ゴミとして扱われる場合があります。粗大ゴミの場合は、事前の申し込みや処理券の購入が必要になることが一般的です。
電池の取り外し 電池で動くインターホンやリモコンに使われている電池は、必ず取り外してから本体を処分してください。電池は別途、地域の指示に従って処分します。
小型家電リサイクル法を活用
インターホンは「小型家電リサイクル法」の対象品目となる可能性があります。この法律は、小型家電に含まれる貴金属やレアメタルなどの貴重な資源をリサイクルすることを目的としています。
回収ボックス 地域の施設や一部の家電量販店などに設置されている専用の回収ボックスに投入します。手続きは不要で、無料で処分できます。
家電量販店での引き取り 新しいインターホンを購入した店舗で、古いものを引き取ってもらえる場合があります(有料の場合もあります)。
認定事業者による回収 国の認定を受けたリサイクル事業者に回収を依頼する方法もあります。
有害物質の適正処理 インターホンの基板には鉛などの有害物質が含まれている場合があり、これらの適切な処理は環境保護の観点からも重要です。
交換業者による引き取り
インターホン交換を専門業者に依頼した場合、古いインターホンを有料または無料で引き取ってくれることがあります。見積もり時や契約時に確認しておくと良いでしょう。これが最も手間のかからない方法の一つです。
その他の処分方法
不用品回収業者への依頼 引っ越しや大掃除などで他にも不用品がある場合は、不用品回収業者にまとめて回収を依頼することも可能です。ただし、インターホン単体の回収では割高になることがあるため、費用を確認しましょう。
売却という選択肢 まだ使用できる状態の良いインターホンであれば、フリマアプリやネットオークション、リサイクルショップで売却できる可能性もあります。ただし、個人情報が含まれていないか、動作に問題がないかなどを確認する必要があります。
部品の分別 地域の指示によっては、プラスチック部分、金属部分、基板などを分別して出す必要がある場合もあります。可能な範囲で分別し、リサイクルに協力しましょう。
どの処分方法を選ぶにしても、不法投棄は絶対に避け、環境に配慮した適切な処理を心がけましょう。
残った部品の対処法
インターホンを交換した際に、古い配線の一部が壁の中に残ってしまうことがあります。
壁内に残る古い配線 特に配線直結式からコンセント式やワイヤレス式に変更した場合など、既存の電源線やチャイムコードが不要になることがあります。これらの配線が壁の中に残る場合、先端がむき出しになっているとショートや感電の危険があるため、必ず絶縁テープなどで安全な状態にしておく必要があります。不安な場合は、交換作業を依頼した業者に処理をお願いしましょう。
交換後のトラブル対処法
新しいインターホンに交換した後、まれに不具合が起きることがあります。慌てずに原因を見つけて、対処しましょう。
電源が入らない場合
確認すべきポイント
- 室内機の電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか
- 電池式の場合、電池が正しくセットされているか、電池の向きは正しいか、電池残量はあるか
- 配線直結式の場合、ブレーカーが落ちていないか
- 室内機の電源スイッチがオフになっていないか
対処方法 上記を確認し、問題があれば修正します。
音が鳴らない・小さい・途切れる場合
確認すべきポイント
- 室内機や玄関機の音量設定が小さすぎたり、消音になっていないか
- 室内機と玄関機間の配線(チャイムコード)が正しく、しっかりと接続されているか
- ワイヤレスの場合、室内機と玄関機の距離が遠すぎないか、間に電波を遮るものがないか
対処方法 音量設定を調整します。配線接続を再確認し、緩んでいる場合は締め直します。ワイヤレスの場合は設置場所を見直します。
画面に映像が映らない・乱れる場合
確認すべきポイント
- 玄関機のカメラレンズが汚れていないか、または結露していないか
- 室内機と玄関機間の配線が正しく、しっかりと接続されているか
- 室内機の画面設定(明るさ、コントラストなど)が適切か
- カメラの前に障害物がないか
対処方法 レンズを清掃します。配線接続を再確認します。画面設定を調整します。
インターホンが勝手に鳴る・鳴りっぱなしになる場合
考えられる原因
- 呼び出しボタンが押し込まれたまま戻らない状態
- 玄関機内部に雨水、砂、虫などが入り込んでいる
- 寒暖差により玄関機内部が結露している
- 配線の接触不良、ショート、劣化
- ワイヤレスの場合、他の無線機器からの電波干渉
- いたずら
対処方法
- ボタンが固まっている場合は、ボタンを何度か強く押してみる
- 異物混入や結露が疑われる場合は、可能であれば玄関機カバーを開けて内部を清掃・乾燥させる(分解は慎重に)
- 配線を確認し、緩みや損傷がないかチェックする
- 電波干渉の場合は、インターホンや他の無線機器の位置を変えてみる
- いたずらの場合は、カメラ付きインターホンであれば録画映像を確認し、必要であれば警察に相談する
応急処置 電源プラグを抜くかブレーカーを落とすことで音を止めることはできますが、来客に気づけなくなるため注意が必要です。
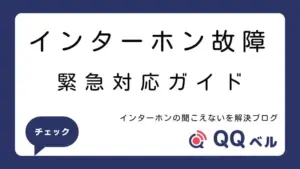
保証の活用
メーカー保証 自分で交換した場合でも、製品自体の初期不良であればメーカー保証の対象となる可能性があります。保証書と購入時のレシートを保管しておきましょう。
インターホンのメーカー一覧はこちらです。
工事保証 業者に依頼した場合は、工事保証が付いているか確認し、取り付け工事に起因する不具合であれば業者に対応を依頼します。
交換作業が中断した場合の対処法
自分で交換作業をしている途中で、部品が足りない、配線が分からない、手順が分からなくなるなど、作業が中断してしまうこともあります。
安全確保を最優先に
まず、感電などの危険がないように、電源プラグを抜く、電池を外す、またはブレーカーを落とすなど、電源がしっかりと遮断されている状態にしてください。
現状把握と記録
何が問題で作業が中断しているのか、現在の配線状況や取り付け状況などを落ち着いて確認し、写真などで記録しておくと、後で専門家に見せる際に役立ちます。
取扱説明書の再確認
もう一度、インターホンの取扱説明書や、事前に参考にした手順書などをじっくり読み返してみましょう。見落としていた点や勘違いしていた点が見つかるかもしれません。
メーカーサポートへの問い合わせ
製品に関する疑問であれば、メーカーのサポートセンターに電話やメールで問い合わせてみるのも一つの方法です。機種名や状況を正確に伝えましょう。
| メーカー名 | URL (確認済み) | 問い合わせ電話番号 (確認済み・備考) | 受付時間 (判明分) | 問い合わせフォームURL (確認済み・備考) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック(Panasonic) | https://panasonic.jp/door/ | 商品全般: 0120-878-983 修理相談: 0120-878-554 マンションHAシステム・集合住宅用インターホン (法人様向け): 0120-187-431 (上記番号利用不可の場合: 06-6904-4574) | 商品全般: 月-土 9-18時 (日祝・正月三が日除く) 修理相談: 年中無休 9-18時 マンションHA: 月-土 9-18時 (日祝・正月三が日除く) | インターホン/テレビドアホン (VL/HA品番): https://jpn.faq.panasonic.com/app/ask/p/1707/ マンション用テレビドアホン/インターホン (WQ品番): https://www2.panasonic.biz/jp/member/inqform/a2A/Consumer |
| アイホン(AIPHONE) | https://www.aiphone.co.jp/ | お客様相談センター: 0120-141-092 (携帯・PHSからは 0565-43-1390) | 午前9:00~午後5:30 (土日祝日・お盆年末年始・GW除く) | よくあるご質問(FAQ): https://www.aiphone-faq.jp/faq/show/ 修理のお申し込み: https://www.aiphone.co.jp/support/contact_repair/ |
| アイリスオーヤマ | https://www.irisohyama.co.jp/ | アイリスコール (製品全般): 0120-211-299 家電専用アイリスコール: 0800-170-7070 | 製品全般: 9-17時 (年末年始・夏季休業・会社都合休日除く) 家電専用: 9-17時 (土日祝除く) | AIチャットボット・自動音声受付: https://www.irisohyama.co.jp/support/ (具体的なフォームURLは案内されず、チャットボット経由での誘導) |
| 朝日電器(ELPA) | https://www.elpa.co.jp/ | 製品に関するお問い合わせ: 042-473-0159 | 平日 9-17時半 (土日祝日・年末年始除く) | https://www.elpa.co.jp/inquiry/ |
| オーム電機(OHM) | https://www.ohm-electric.co.jp/ | お客様相談室 (フリーダイヤル): 0120-963-006 (携帯電話・IP電話など): 048-992-2735 | 平日 9-17時 (土日祝日・年末年始除く) | https://www.ohm-electric.co.jp/cgi/ssl_customer/support_SSL.html (製品のお問い合わせ) |
| NASTA(ナスタ) | https://www.nasta.co.jp/ | インターホンに関するお問い合わせ (設置後): 0570-023-654 その他製品・支店代表: 地域別番号あり (例: 東京支店 03-3660-1815) | AM 9:00 – PM 5:00 (支店による) 。 0570-001-350という番号も存在 | インターホンのお問い合わせについて: https://www.nasta.co.jp/support/about-interphone/ |
| DXアンテナ | https://www.dxantenna.co.jp/ | DXアンテナ・デルカテック製品 お客様ご相談窓口 (ナビダイヤル): 0570-033-083 (上記ナビダイヤル利用不可の場合): 050-3818-9016 | 9:30-17:00 (夏期・年末年始休暇除く) | https://www.dxantenna.co.jp/support/ |
| ユニデン(Uniden) | https://unidenholdings.jp/ | サポートダイヤル: 03-5543-2232 | 9:30-17:00 (土日祝日・弊社休業日除く) | https://unidenholdings.jp//toiawase/toiawase_form01/ (製品サポートお問い合わせフォーム) |
| カシムラ(KASHIMURA) | https://www.kashimura.com/ | サポートお問い合わせ: 050-3199-2558 | 月-金 10-12時, 13-17時 (土日祝除く) | https://www.kashimura.com/contact/ |
| ツインバード(TWINBIRD) | https://www.twinbird.jp/ | お客様サービス係 (調理・空調等): 0120-337-455 (固定電話) / 0570-037-455 (携帯電話・ナビダイヤル) (冷凍冷蔵庫・洗濯機専用): 0120-060-620 (固定電話) / 0570-060-620 (携帯電話・ナビダイヤル) | 調理・空調等: 平日 月-金 9-17時 冷凍冷蔵庫等: 平日 9-18時, 土日祝 9-17時 | https://www.twinbird.jp/support/inquiry/ |
| 日本アンテナ | https://www.nippon-antenna.co.jp/ | 製品・受信について (ナビダイヤル): 0570-091039 (上記ナビダイヤル利用不可の場合): 03-3893-5243 | 9-12時, 13-17:30 (土日祝祭日・弊社休業日除く) | https://www.nippon-antenna.co.jp/ja/contact.html#product (商品に関するお問い合わせ) |
| マスプロ電工 | https://www.maspro.co.jp/ | お客様ご相談窓口 (ナビダイヤル): 0570-091119 (上記ナビダイヤル利用不可の場合): 052-805-3366 | 9-12時, 13-17時 (土日祝日・弊社休業日除く) | https://www.maspro.co.jp/contact/ (総合お問い合わせ窓口) (製品分野別フォームあり) |
| NIC株式会社 | http://telecall.co.jp | 042-649-8501 | 不明 | nic-info@telecall.co.jp (メールアドレス) |
| 株式会社ジェイ・ティ・エス | https://www.j-ts.com/ | オペレーションセンター: 045-264-6440 | 土日祝日・年末年始除く | https://www.j-ts.com/contact (お問い合わせフォーム) info@www.j-ts.com (メールアドレス) |
| 更科製作所 | https://sarashina-s.co.jp/product/door-phone/ | 0256-62-4649 | 平日8-17時 | https://go.sarashina-s.co.jp/contact/ (お問い合わせ・資料請求フォーム) info@sarashina-s.co.jp (メールアドレス) |
| ダイトク | https://www.daitoku-p.co.jp/ | お客様相談窓口: 0120-318-544 | 9-17時 | https://www.daitoku-p.co.jp/PostMail/ info@daitoku-p.co.jp (メールアドレス) |
| ケアコム | https://www.carecom.jp/ | コールセンター (フリーダイヤル): 0120-711-107 コールセンター (直通): 042-485-7316 保守サービス (本社内): 042-485-7306 | 保守サービス: 8:45-17:30 | https://www.carecom.jp/inquiry/product-input/ (製品・システムに関するお問い合わせ) |
| プラネックスコミュニケーションズ | https://www.planex.co.jp/ | サポートダイヤル (ナビダイヤル): 0570-064-707 | 月-金 10-12時, 13-17時 (祝祭日・弊社指定休業日除く) | http://www.planex.co.jp/support/techform/ (技術お問い合わせフォーム) |
| リーベックス | https://revex.jp | サポート係 (ナビダイヤル): 0570-666-365 (ガイダンス2番-2番) | 平日10-12時, 13-16時 | https://revex.jp/contact/ |
| シャープ (Sharp) | https://jp.sharp/support/tel/option/doorphone.html | 0120-663-700 (固定電話フリーダイヤル, お客様ご相談窓口) 0570-550-194 (携帯電話ナビダイヤル) | 月曜~土曜: 9:00~18:00 日曜・祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く) | https://jp.sharp/support/inq_com02.html ドアホン問い合わせ: https://jp.sharp/support/tel/option/doorphone.html |
| 東芝 (Toshiba) | https://www.tlt.co.jp/tlt/ | 0120-66-1048 (フリーダイヤル, 東芝ライテック商品ご相談センター) 046-862-2772 (携帯電話など, 有料) | 9:00~18:00 (日曜, 祝日, 年末年始を除く) | https://www.tlt.co.jp/tlt/support/support.htm |
部品の問題への対処
部品破損・不足の場合 作業中に部品を壊してしまったり、必要な部品が足りないことに気づいた場合は、メーカーから直接部品を購入できるか確認するか、家電量販店、ホームセンター、オンラインの部品通販サイトなどで代替品や追加部品を探します。その際、正しい型番や仕様を確認することが重要です。
リセット操作
一部のインターホンにはリセットボタンがあったり、電源の再投入で初期化されたりする場合があります。取扱説明書でリセット方法を確認し、試してみるのも有効です。
専門業者への依頼
どうしても自分での解決が難しいと判断した場合は、無理に作業を続けず、専門の電気工事業者に作業の引き継ぎや点検・修理を依頼するのが最も安全な方法です。その際、これまでの作業内容や問題点を正確に伝えることで、スムーズな対応が期待できます。
まとめ
インターホン交換は、本体の交換だけでなく、古い機器の適切な処分と、交換後のトラブル対応も重要な要素です。
処分については
- 地域のルールに従った適切な処分
- リサイクル法の活用
- 環境への配慮
トラブル対応については
- 慌てずに原因を確認
- 基本的なチェックポイントの確認
- 保証の活用
- 困った時は専門家に相談
これらのポイントを押さえることで、インターホン交換を最後まで安心して完了できます。自分で作業する場合は、事前の準備と慎重な作業、そしてトラブル発生時の冷静な対応が成功の鍵となります。
まとめ:最適なインターホン交換で安心な毎日を
インターホンの交換は、単に古くなった機器を新しくするだけではありません。お家の安全性を高め、毎日の生活をもっと便利にし、ご家族みんなが安心して暮らすための大切な投資です。この記事では、交換を考えるきっかけから実際の作業、そして交換後のお手入れまで、幅広く紹介してきました。
インターホン交換で得られるメリット
新しいインターホンは、あなたの暮らしを大きく変えてくれます。
安全性の向上
はっきりとしたカメラ映像で訪問者をしっかり確認でき、録画機能でお留守の時も安心です。知らない人が来ても、ドアを開けずに安全に対応できます。
生活の便利さアップ
スマートフォンと連携できるタイプなら、お買い物中やお仕事中でも自宅への来客に対応できます。宅配便の時間を気にしなくても良くなり、ご家族の見守りにも役立ちます。
毎日の安心感
これらの機能により、日々の暮らしがより安全で快適になります。特に、一人暮らしの方や小さなお子さん、ご高齢の方がいるご家庭では、大きな安心感を得られるでしょう。
自分に合った方法と機種を選ぶことの大切さ
交換方法の選択
自分で交換すれば費用を抑えられますが、壁の配線に直接つながっているタイプの場合は電気工事士の資格が必要です。安全面や仕上がりの良さを考えると、専門業者にお願いするのがおすすめのケースも多くあります。
機種選びのポイント
たくさんの種類があるインターホンの中から、ご家族の構成、生活スタイル、そして最も重視したい機能(防犯、便利さ、見守りなど)を考えて最適な一台を選ぶことが、交換後の満足度を大きく左右します。
予算との兼ね合い
高機能なものほど便利ですが、必要以上の機能にお金をかける必要はありません。ご家庭に本当に必要な機能を見極めることが大切です。
住まいのタイプに応じた配慮
戸建て住宅
比較的自由に交換できますが、設置場所や防水対策をしっかり考える必要があります。
マンション・集合住宅
管理組合への相談や承認が必要な場合が多く、オートロックとの連携も考慮する必要があります。
賃貸物件
大家さんや管理会社への許可が必須で、退去時の原状回復も考える必要があります。
安全で快適な生活のために
情報収集の大切さ
インターホン交換は頻繁に行うものではありません。だからこそ、この記事の情報を参考に、しっかりと調べて、ご自身の状況に合わせて慎重に判断することが重要です。
安全第一の考え方
自分で作業する方は何よりも安全を第一に考え、少しでも不安があれば無理をせず専門家に相談してください。
信頼できる業者選び
業者に依頼する方は、資格の確認、複数の見積もり比較、保証内容の確認を怠らず、信頼できる業者を選びましょう。
長期的な視点での投資
10年以上使う設備
インターホンは一度交換すれば10年以上使い続ける設備です。初期費用だけでなく、長期間の使いやすさや満足度を考えて選択しましょう。
家族の成長に合わせて
お子さんの成長やご家族の年齢を考慮し、将来も使いやすい機能を選ぶことで、長期間にわたって快適にお使いいただけます。
メンテナンスの重要性
設置後も定期的な清掃や点検することで、長持ちさせ、いつでも最高の性能を発揮できます。
新しい生活のスタート
インターホン交換は、新しい生活スタイルの始まりでもあります。より安全で便利で快適な毎日を手に入れるための第一歩として、この記事で紹介した内容を活用していただければと思います。
家族みんなで話し合って
どんな機能が欲しいか、どこに設置するかなど、ご家族みんなで話し合って決めることで、全員が満足できるインターホンを選べます。
専門家のアドバイスも活用
分からないことがあれば、遠慮なく販売店や施工業者に相談しましょう。専門家のアドバイスが、最適な選択につながります。
最適なインターホン交換を通じて、皆様がより安心で快適な毎日を送れることを心より願っています。新しいインターホンとともに、素晴らしい暮らしをお楽しみください。インターホンが聞こえない問題をまとめて知りたい方はこちら(総合ガイド)

